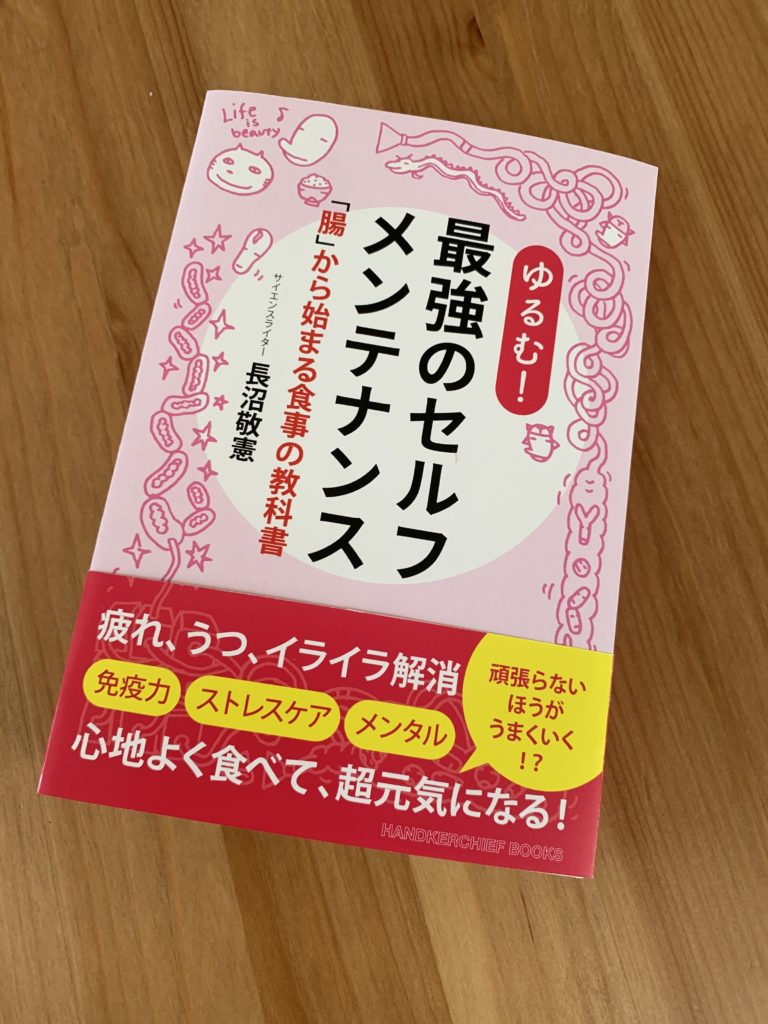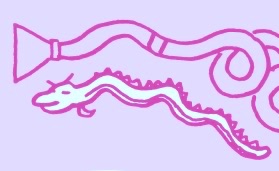「サンデーモーニング〜風をよむ」で生命誌・中村桂子先生が語った「ウイルスとの共生」について考えてみた。
ちょっと前に日曜朝の「サンデーモーニング」を何気なく見ていたら、最後の「風をよむ」に生命誌研究館の中村桂子先生が出演されていました。
テーマは、いまの世の中にドンピシャの「ウイルス・細菌と人類」。
このテーマで中村先生を起用するってセンスいいな〜と思いつつぼんやり見ていたら、過去に「TISSUE」でインタビューした時のこととか、禅僧・藤田一照さんとの対談を企画してイベントやったこととか、いろいろと思い浮かんできました。
あれ、そう言えば中村先生って、あの時、オリンピックのことで面白いこと言っていたな。そう思って掲載誌を読み返してみたら、こんなことが書かれてました。
中村 私はね、ノーベル賞とオリンピックは20世紀で終わりだと思っているんです。20世紀においてはノーベル賞も素晴らしいことだったと思いますが、もうあのタイプの仕事は終わりです。だって、たとえば科学の仕事だって、ニュートリノを探すのにカミオカンデを使わないとできないんですよ。やっぱりノーベル賞はアインシュタインにあげるべきでしょう?
――いまは個人の業績よりも、そうした大規模研究が大事になっていますよね。
中村 カミオカンデを作ってニュートリノを探すことは、もちろん大事です。それはやってもいい。だけど、もうそういう時代になったんだから、20世紀型のノーベル賞は終わりましょうよ。良い功績を出した人には、21世紀型のご褒美をあげるシステムをべつに作ればいいんですよ。
「これからは『普通に生きる』ための決心が必要かもしれません」(中村桂子インタビュー②)
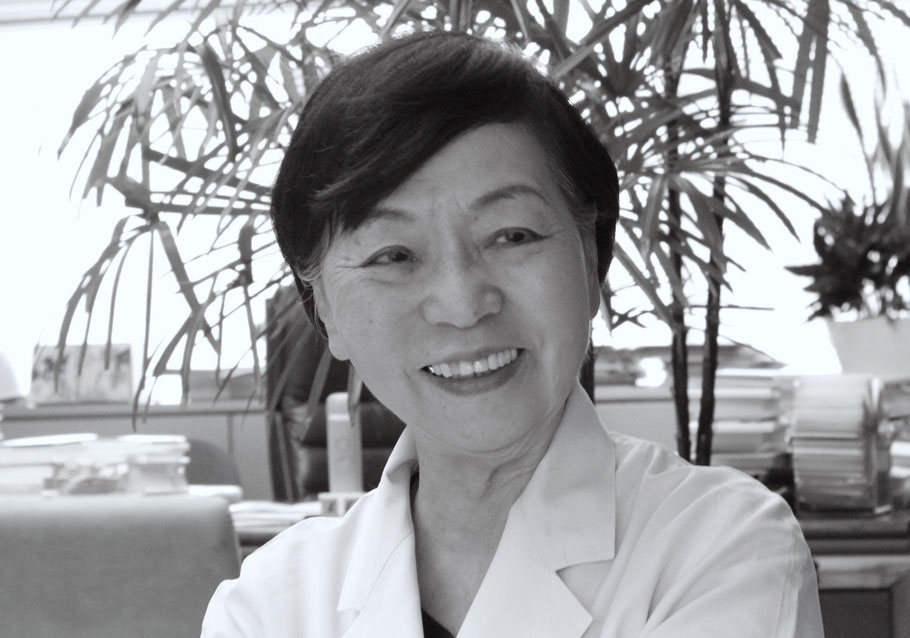
なるほど〜。今回のオリンピック延期を考えたら、このあたりの発言ってかなりの先見の明を感じますよね。
良い功績を出した人には、21世紀型のご褒美をあげるシステムをべつに作ればいいんですよ。
21世紀型のご褒美って何でしょうね? 。。。もしかしたら、いま、そのことを考える時間が与えられているのかもしれません。
自粛モードの中、僕がいまゆっくり読んでいるのはこちら。ここに出てくるeumo(ユーモ)って、ご褒美の新しいカタチにもつながってきそうですよね。
で、このあたりの話はまた別の機会にするとして(まだ読み終えてないので)。。。ここでは中村先生の番組でのコメントをたどっていきましょう。「サンデーモーニング」スタッフノートという素敵なページを見つけたので、テーマである「ウイルス・細菌」にまつわる箇所を抜粋すると。。。
自然の中にはバクテリア(細菌)がいたり、ウイルスがいたり、いろんなものがいるわけで、人類がこの地球上に登場した時には、もうそういうものはいた。ある意味では時々戦ったり、ずっと長い間、一緒に生きてきた。
ずっと長い間、一緒に生きてきた。。。時々戦ったりすることはあっても、ずっと「敵」だったわけではなく、あくまでも共生がベース。
狩猟・採集社会の時は、バラバラだから気にしなくてよかったんだけど、農業を始めて、割合、密に暮らすようになって、さらに都市を作って、もっと、密に暮らすようになった。そうするとあちら側(ウイルスなど)から見ると感染しやすい。
私たち(人間)はすぐに役に立つか?とか、必要か?っていうけど、自然界にいる以上、全てのものが、いることに意味があるので、別に必要だから、いるわけでも何でもない。私、いるから、いますよってわけで。。。
病原体として出てきた時には、なるべく減らさなくてはいけないし、そういう意味では戦わなきゃいけないが、ゼロにしちゃう、何もなくなる、それが良いわけではない。そういうもの(ウイルスなど)がいる世界で、(人間も)生きているんだよなぁ、という感覚は持ち続けないと生きているということにはならない。
私、いるから、いますよって。。。笑。ウイルス感染を何とか終息させたいと思っている人からみたら、不謹慎な発言? でも、いるからいるものをコントロールするよりも、どうやって一緒にいられるか、共存できるか?
こういう発想をしていかないと、現実問題やってはいけないし、そもそも封じ込めなんてできるはずはないと思いませんか?
まあ、戦略的にやっているということなんでしょうけど、僕からしたら「共存できる体内環境をつくればいい」って、改めて思います。
生命の歴史をふまえたら、そのほうがむしろ戦略的じゃないですか。
で、その戦略の一つがこのブログで繰り返し書いてきた「セルフメンテナンス」ということになるわけですが。。。ここではそっちの話には踏み込まず、「物の見方、価値観」にフォーカスしてみましょう。
そもそもウイルスがこんなふうに繁栄する背景には、中村先生がおっしゃていたように、僕たち人間の暮らしがあったりするわけです。
文明化が進み、経済が発展することで生態系のバランスが崩れたことはよく指摘されていますが、大事なのは「暮らしの変化の背後には意識の変化があった」ということ。
意識の変化は、価値観の変化と言ってもいいかもしれません。
感染症にしても、細菌やウイルスをいかに撲滅するか、制圧させるかという近代医学の「価値観」の上に成り立ってきたわけですが。。。その一方で「共生や多様性が大事」ということも言われるようになってきましたよね。
いま、新型コロナウイルスのパンデミックを通じて、この二つの価値観がせめぎ合い、矛盾が浮きびりになってきているように感じます。
――先生は、「人間は生き物であり、自然のなかにいる」ということを話されていますよね?
中村 そうです。私が思っているのはそれだけです。だけど、先ほども話したように、抽象的に「生命を尊重しよう」と言っても私にはピンと来ない。「生命尊重って何?」って考えた時に、たとえば、ここに蟻が這っているとするでしょう。この蟻も親がいないと存在しませんが、その親の親のことを考えていくと38億年もさかのぼれるんですよ。つまり、目の前の小さな蟻も38億年かからないとここにはいない。それってすごいことですよね?
――生命尊重が実感につながっていきますね。
中村 どんなに立派なロボットも、パーツをひとつずつ組み立てればできてしまうけれど、38億年はかからないですよね? でも、蟻は38億年がないとここにいない。すごいことだけれども、同時にそれは当たり前のことでしょう? もちろん、人間もそのひとつであって、生き物であり、自然の一部なんです。そういうことをベースに生きていくということは、当たり前なんだということです。
――科学では、論文を書くにしても数量化って絶対に必要じゃないですか? ただ、それだけでいいのかという話につながりますよね?
中村 そうです。
――その部分が伝わりそうで伝わっていないような気がするんですが?
中村 自分の持っている世界観が決まっていればいいだろうと思うのです。数値は出さなければいけませんが、問題は自分の持っている世界観です。世界観が生き物の世界観であれば、数値はそこに吸収できます。
でも、それが機械のような世界観で、こんなに格差があっても平気な世界観を持っていたら、同じ数値が違う意味を持ってしまうでしょう? ここでも毎日DNAを分析しているわけで、やることの問題ではないんです。
問題は自分の持っている世界観です。それが生きるということをベースにした世界観になっていない、そこが問題なんです。
「自分の世界観が決まっていればいいんです。数値は出さなければいけませんが、問題は自分の世界観です」(中村桂子インタビュー①)
いま、コロナウイルスと向き合っている皆さん一人一人、どんな「世界観」を持っているでしょうか?
ウイルスなんて邪魔だから消えてなくなってしまえ!という世界観?
ワクチンでも治療薬でも早く開発して、追い出してくれ!という世界観?
ここではワクチンや治療薬を批判しているわけではなく、こういう「考え方」についてフォーカスしているわけですが。。。ピンと来るでしょうか?
だって、共生なんですよね、大事なのは。
ウイルスと共生? でも、感染症が大きな問題にならない限り、多くの場合、それが当たり前の日常であるわけです。それがなぜ、人間社会の経済活動を一斉に自粛させてしまうようなクライシスにつながってしまったのか?
そう考えていくと、ウイルスが暴れ出すことで、いま世界観そのものの変更が迫られているのを感じませんか?
ここまでのロジックをふまえるならば。。。
もともとあった世界観(科学技術、経済の拡大発展で自然をうまくコントロールしようというような発想)の延長上に今回のパンデミックがあるのはもちろん、感染症対策自体、これまでの世界観の枠内にあるのかもしれません。
有識者と呼ばれる人たちの発言だってそう。
腸内細菌との共生が大事だと言っておきながら、他方、現代医療ではその菌たちを殺してしまう抗生物質が当たり前のように使われている。
ワクチンの話と同様、抗生物質の副作用が怖いとか、健康を害すると言ってるわけではないですよ。
そうではなく、問題となるのはあくまで考え方、価値観、世界観。。。
自然とつながるってどういうこと? それとウイルス感染に対処することをどうつなげたらいい? 中村先生は、恩師の一人であった哲学者の大森荘蔵先生の言葉を借りながら、こんなことを話されています。
――先ほどの大森荘蔵先生が、「略画」と「密画」という言葉を使っておられますよね?
中村 自分の目で見たり、耳で感じたり、手で触れたりすることで描かれる世界像が「略画」、望遠鏡や顕微鏡を利用して対象を細部までとらえる世界像が「密画」、大森先生はそう語っていますね。日常が略画、科学が密画という分け方もできますから、今日のお話のキーワードにもなると思います。
――数量化の問題も密画のなかにありますから……。
中村 ただ、密画はしっかり書かなきゃいけません。科学って密画ですからね。
――でも、死物化してしまうことの問題を、大森先生は指摘されていますよね?
中村 だから、そこへ自分の世界観を持ってきて、略画と重ねるんです。その時に世界観が出せる。これはある意味では技術ですよ。
要するに、略画が世界観で、そこに密画を重ね描きすることが大事なんです。これを無視して、科学をただ悪者みたいに言ってもしかたがありません。科学は密画として、きちっと数量を出して描いていくものです。それに略画をちゃんと重ねましょうということなんです。
「これからは『普通に生きる』ための決心が必要かもしれません」(中村桂子インタビュー②)
密画(科学)と略画(世界観)の重ね合わせ、つまり、統合。。。
感染症と人の関わりについて言えば、それは「近代医学が積み重ねてきた公衆衛生的な知識と経験」、そして「古い時代から受け継がれてきたセルフメンテナンス(養生)の知恵」、この二つを車の両輪とするということ。
中村先生がどう感じられているかわかりませんが。。。「三密」の大切さを説き、「手洗い」や「マスク」の話ばかりするいまの感染症対策は、統合的な視点では「片輪だけで車を走らせる」ようなもの。
正確に言えば、セルフメンテナンスだって密画的な領域(エビデンス)と略画的な領域(経験値)の両輪がある以上、その統合が求められることになりますが。。。
いずれにせよ、物の見方の根本的な変更が迫られていることが見えてきませんか?
そう、新しい世界はすでにもう目の前に現れているのです、ウイルスによって。目を開けばそれは見えるところにあるのだから、目を開けてみましょう。
僕自身、目の前に現れている新しい景色がどんなものなのか、これからもいろいろな形で伝えていきたいと思っています。
大事なのは統合する視点、まなざしです。そうした感覚を身につけ、これまでの知識や知恵をフルに活かしていくことです。
で、例によってになりますが。。。とりあえずセルフメンテナンスの詳細については、こちらをポチっとお願いします。笑。(本日、発売になりました〜!)
★『ゆるむ! 最強のセルフメンテナンス〜「腸」から始まる食事の教科書』